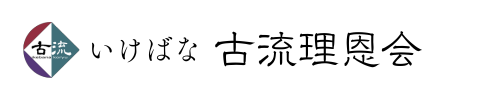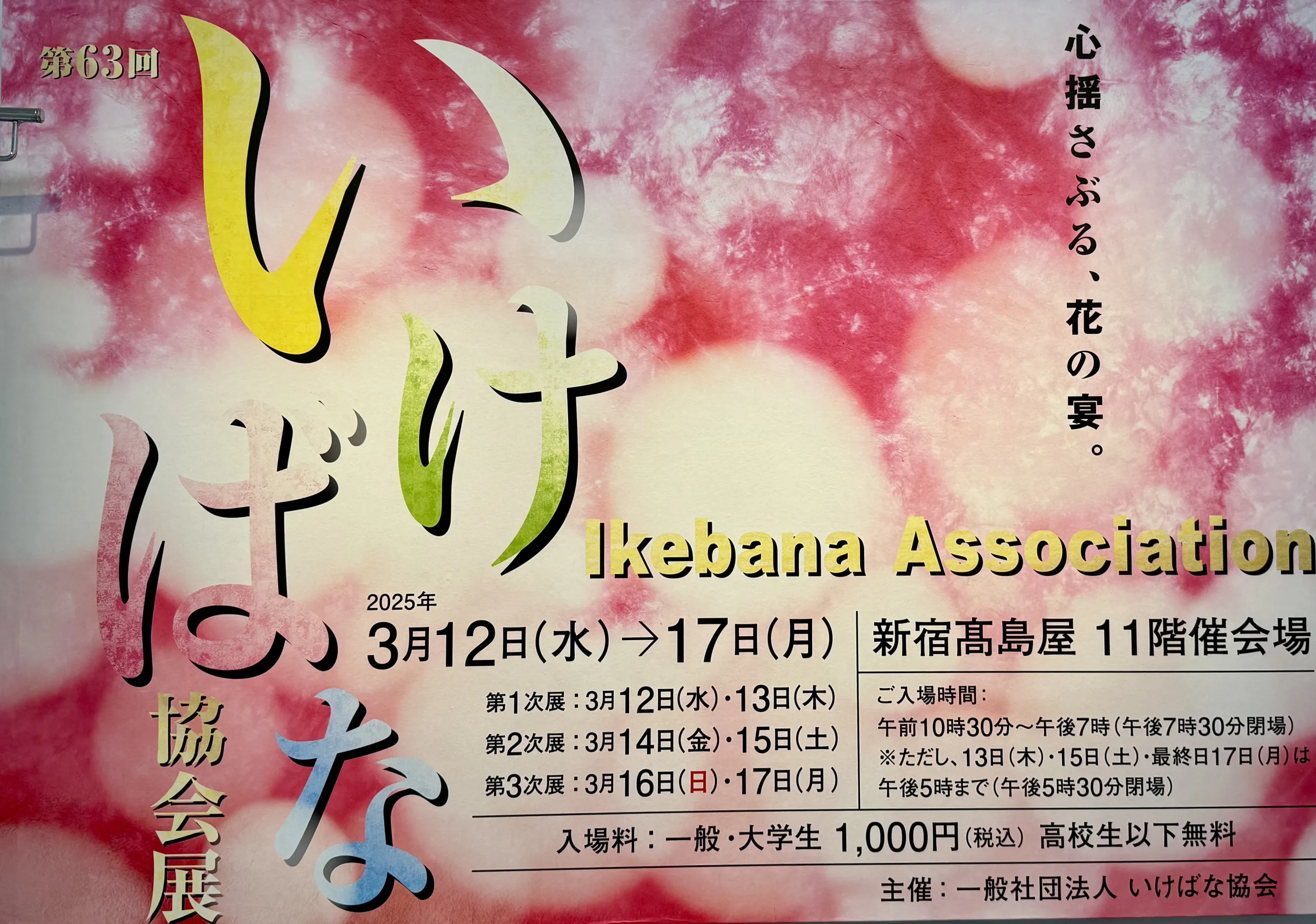桜は日本の花の代表と言える花です。
満開になると、雪が積もったかのようにあたり一面が真っ白になります。
古くから人々に愛され、歌に詠われてきました。
「花見」といえば桜の花を見ることをさします。
桜について
桜は、バラ科サクラ亜科サクラ属(Prunus subg. Cerasus)の落葉高木、または低木です。日本に自生する10種を中心に、自然交配種や園芸交配種が300種ほどあると言われています。
桜の種類
自生種とは人により移入されたものではなく、古くからその場に生息している種類です。
交配種は自然に交配されたもの(自然交配種)と人工的に交配し固定された種(園芸種)です
山桜(ヤマザクラ)自生種

ヤマザクラは最も代表的な種類で、古くから詩や歌に詠まれ、親しまれてきました。山地に広く自生し、関東、中部から南の地域によく見られます。
花と同時に葉が出るのが特徴で、花弁は5枚、色の変異が多く、白色や先端だけ色が濃い花を咲かせる場合もあります。葉色は赤紫色や褐色など、さまざまに色が変化します。樹皮は丈夫なので、工芸品などの材料としても利用されています。
染井吉野(ソメイヨシノ)園芸種

ソメイヨシノは日本で最も有名な桜であり、日本固有の桜とされています。江戸末期~明治初期頃に現在の東京の駒込にあった染井村の植木職人や造園師が、オオシマザクラとエドヒガンを交配させてつくったと言われています。花弁は5枚あり、咲き始めは淡い赤色で、満開になると白色に近い色になります。桜の開花日を予想する「桜前線」もソメイヨシノの開花を基準にしています。
八重桜(やえさくら) 園芸種

八重桜は通常の桜が花弁が5枚に対して、それ以上の桜を指します。多くの園芸品種が作られています。
「寒山」「一葉」「普賢象」「鬱金」「御衣黄」「天の川」などがあります。
花期は一般的に遅く、染井吉野の開花後に咲きます。
江戸彼岸(エドヒガン)自生種

エドヒガンザクラは、本州・四国・九州の山地でよく見られる種類で、樹高は15~25m、楕円形の葉と花の基部が膨らんでいるのが特徴です。花弁は5枚で一重、色は薄紅色から白に変わります。丈夫で花がたくさん咲くため、多くの品種の母種として使われ、ソメイヨシノの片親としても有名です。日本の三大桜国の天然記念物もこの江戸彼岸種です
山梨県山高「神代桜(やまたかじんだいざくら)」
岐阜県根尾谷「淡墨桜(うすずみざくら)」
福島県「三春滝桜(みはるたきざくら)」
寒緋(カンヒ)自生種

カンヒザクラは沖縄でよく見られる桜で、早咲きとして有名な「河津桜(カワヅザクラ)」の交配元です。花の色は赤紫色ですが、ときに白色や色の淡いものなどもあります。開花後、花は釣り鐘のように垂れ下がっていき、花の大きさは小ぶりで、樹高も他と比べて約5mと低いのが特徴です。
実桜(ミザクラ)園芸種

実をさくらんぼとして食べるために改良された桜。日本のさくらんぼはほとんどが西洋実桜を改良したものです。
「佐藤錦」「紅ゆたか」「高砂」「紅さやか」「ナポレオン」などがあります。
桜と文化
「さくら」の語源には「さ」(稲を表す)「くら」(神のおります所=くら)といわれています。古くから農業と関わりが深い木で、桜の花が咲くのを合図に農作業を行っていました。「こぶし」の花を「さくら」と呼ぶ地域もあるそうです。
花見

「花見」といえば桜の花を指しますが、元来は桜の花の咲き具合をみて、その年の農作物の豊凶を予想するものでした。
平安の頃の貴族が桜の花を愛でながら、酒宴を開いた風習が合わさり、現在の「花見」になったといわれています。
和歌

万葉集などでは中国渡来の「梅」が花の代表として詠まれていましたが、平安時代になると春の季語として定着しました。
また、西行法師は「吉野の桜」を愛で、辞世の句として「願はくは花の下にて春死なんそのきさらぎの望月のころ」は有名です。
文学

「桜」の花のパッと咲いて、散っていく姿は「諸行無常」であり、「儚い人生の投影」として、「もののあわれ」を象徴する日本人の精神性の表れとして多くの文学でも扱われて来ました。
「花は桜木、人は武士」(花のなかでは、ぱっと咲いてぱっと散る桜の花がいちばんであるが、人の最もみごとな生き方は、美しく咲いて潔く散る武士であろうというたとえ)
生活

「桜」の葉(大島桜)は塩付けにして「桜餅」に、花も「桜湯」として、また、実(実桜)は「さくらんぼ」として食用にします。
木材は家具などの材に、樹皮は「樺細工」や「版木」に使われました。また、樹皮は漢方薬として蕁麻疹や腫れ物などの皮膚薬として用いられました。